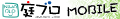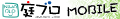チェルノブイリ被害視察の福島県調査団―清水修二団長に聞く

福島県のチェルノブイリ原発事故調査団が十一月、深刻な被害を受けたベラルーシ、ウクライナを視察した。現場には石棺で覆われた事故炉が残り、放射性物質で汚染されたとされる地域にはなお、ベラルーシだけで約百十四万人が住み続ける。福島第一原発事故で放射線による汚染との"共存"を強いられた福島県はチェルノブイリから何を学ぶのか。調査団長の清水修二・福島大学副学長に聞いた。
「チェルノブイリ原発から約三十キロのベラルーシ東南部コマリン村では、学校に放射性物質についての情報センターが設けられ、子どもたちが各家庭の食料品を持ち寄っては測定器に入れ、放射線量を調査していた。測定器は円換算で一台数十万円ほど。福島市長にさっそく、測定器を福島市内すべての学校に設置してはどうかと提案した。ベラルーシでは農地の除染は行っていない。
一方で平均十一ヘクタールごとの区画に分けて詳細な汚染地図を作り、汚染の状態と土壌の性質を見た上で、作目を選びながら耕作を進めていった。ゼロか百かという考え方ではなく、これは福島の農業復興にとって参考になる。(村域の一部が警戒区域に指定されている)川内村の遠藤雄幸村長が"(毎時放射線量が)一マイクロシーベルトでも村に戻れますか"と質問したのに対し、ベラルーシの専門家は、被ばくリスクのほとんどは内部被ばくによるもの、と説明していた。内部被ばくの大半は食物経由で、空間線量による外部被ばくに比べ、コントロールしやすい。学校など身近な場所で、自分で測って納得できる仕組みをつくることが重要だ。
(中略)
福島第一原発事故で、一万人を超える子どもたちが福島県外に出て行ってしまい、事故前約二百二万人だった県の人口は百九十九万人を割ってしまった。
避難した人としない人などの人間関係の分断も起きている。"脱原発"を国策に位置付けて原発からの計画的な脱却を図り、負の遺産である放射性廃棄物処理の問題に真面目に取り組むべきだ」
(11.12.19. 東京新聞『こちら特報部』より抜粋)