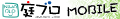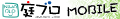「Ss」の1.1倍で壊れる原発
○耐震設計とは
原発の耐震性能を決める手法をまず簡単に説明する。
原発の耐震性を決めるための基礎になる「揺れの大きさ」を「基準地震動・Ss」という。耐震設計審査指針が改定された2006年から適用されており、原発の耐震性能を評価する基準の揺れの大きさを加速度で表現したものだ。それまでの耐震設計審査指針では「設計用最強地震」に対してS1、それより大きい「設計用限界地震」についてはS2という基準が使われていた。Ssの考え方はS2に近いが同じでは無い。
現在の一般建築物においても「レベル1(希に発生する地震動)」「レベル2(極めて希に発生する地震動)」という基準を使っている。おおむねレベル1は200ガルで、損傷を受けないこと。レベル2は400ガルで、倒壊しないことなどとなっている。以前は原発が一般建築物の「3倍程度強固に作っている」と宣伝していた根拠は、このレベル1の3倍程度でも破損せず、レベル2の3倍程度でも倒壊しないという趣旨だったと考えても良いだろう。(3倍というのは単純に600ガルと言うことではない)
地震とは、地下数百キロからゼロキロの間にあるであろう震源断層が活動することにより生ずる。揺れは地盤を通って原発の基礎に到達し、さらに原発内部に侵入して構造物や機器類を揺らす。その際重要なのは、構造物が耐えられるかどうかだ。そのためには耐震力のある設計が必要だ。
理学的にいえば、地震が起きることも、その大きさも、一定の確率の下でしか評価できない。最大限、ある断層が「100%動く」とは言えても、いつ、どれだけの大きさの地震として、と問われれば「わからない」としか言えない。そのため「30年以内に99%」などと表現している。
しかし構造物を作るのに確率は役に立たない。揺れの大きさを特定しないと設計が出来ない。
そのため工学的に「割り切りが必要」と裁判所の法定で堂々と言ったのが斑目春樹原子力安全委員会委員長だった。
ただし、この発言には重大な前提が欠けていた。それは「割り切りが必要な場所」などに、そもそも立地してはならないことだ。「原子力施設の立地指針の判断目安」(64年原子力委員会決定)に、はっきりそう書いてあるのだから反論の余地は無い。
基本的考え方の冒頭に「大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが、将来においてもあるとは考えられないこと。また、災害を拡大するような事象も少ないこと」とあるのだから。
日本で最も巨大かつ頻繁な海溝型地震を起こすとされる場所に、原発を建てることを許可した理由を釈明すべき立場の安全委員長が、「割り切り」と言ったのは浜岡原発に対してだ。驚くべき開き直りと無責任さは、この国の原子力行政のデタラメぶりを象徴するものだ。
○原発の地震動評価手法
原発などの構造物は、一定の条件の下に定める工学的基盤、いわゆる「解放基盤面」において、どれだけの揺れを想定するかにより耐震設計が決まってくる。これは原発ごとに決められる。
「解放基盤面」を決めるのは、地下の地盤の堅さであり、地震の横波と呼ばれるS波(剪断波とも言う)が地中を伝わる速度が毎秒700メートル以上の地盤を「解放基盤面」としている。この値は全国の原発で共通で、従って解放基盤面が地下196メートル以上の場所にある福島第一や、地下8.6メートルのところにある女川原発などの違いが出る。一般的に地下浅いところにあるということは固い地盤がすぐ下にあると言うことであり、100メートル以上も離れている場合は軟弱な地盤であると言えるだろう。
解放基盤面では、地震の際には上に地盤が乗ったまま揺れることになるので、地震の波が地表面に反射して跳ね返り、基盤面の揺れが干渉により変化する。上部地盤の影響を受けてしまうと揺れの大きさや周期などを元に建屋内部の影響を計算し評価することが困難なため、上部地盤を取り除いた「仮想的な地盤」をコンピュータ上で作る。地盤を「はぎ取って」地震波形を作ることになるので、それを「はぎ取り波」という。
この波は単純に「地震加速度600ガル」などという数値ではない。これでは設計は出来ない。ここで言う600ガルというのは、周期0.1秒における地震加速度でしかない。実際に設計する際には、基準地震動の波形を作らなければならない。特に0.3秒や1秒付近の周期でどれだけの大きさの速度、加速度になるかは重要だ。この周期は配管などの構造物や建屋の固有周期が多く存在しているので、共振により損傷することも考慮しなければならない。それら「卓越周期」「周期ごとの加速度、速度」「変位量」などが分からなければ
設計は出来ない。これらを代表して「周期0.1秒の加速度」をSsの数値として発表しているに過ぎない。
なお、中越沖地震を踏まえて現在の柏崎刈羽原発のSsはぎ取り波は実に2280ガルにもなっている。これらを踏まえて以下をお読みください。
○福島第一のSsと実測値
福島第一はSs600ガルに対して実測値は675ガル、さらに震源域に近かった女川ではSs580に対して636ガル、いずれも実測値がSsを上回った。しかし柏崎刈羽原発が2007年に中越沖地震で記録した1699ガル(Ssは以前は600ガル)という大きな差は無かった。
そういう意味では、地震動の大きさは基準地震動を超えたが、そのために機器類が破壊されることは本来は無いはずだった。東電も中間報告で「地震の大きさはほぼ想定通り」と書いたくらいだ。
実際、柏崎刈羽では、2700カ所以上の機器類の破損があった。津波は無かったが地震動だけでも原子炉を破壊する危険性はあった。3号機の起動変圧器は炎上し、外部電源も失われた。非常用ディーゼル発電機も起動したものが多かったが、全体的に電力不足に陥り、タービン駆動給水ポンプを動かすために補助ボイラーが起動したが、1から5号機と6,7号機でそれぞれ一台しか使用できなかった。そのため運転していた3、4号機で一台を取り合う結果となり、起動変圧器が炎上していた3号機を優先したため4号機の冷温停止には丸2日掛かっている。これなど、後一歩深刻な事態に陥っていたら、メルトダウンにはならなかったとしても燃料が露出し損傷する事態に至っていたかもしれない。
しかしこれが教訓にはならなかった。見過ごされた問題は、地震だけで十分深刻な事態になっていたことだ。
いまストレステストが各地の原発で行われているが、そのうち一次テストの結果が公表された大飯原発3、4号機と伊方原発3号機では、最も厳しい配管類についてもSsによる揺れに対して約1.8倍程度の「余裕」があることになっている。

福島第一原発でも現在の大飯原発などで実施されているテストで使われている計算手法を使えば。同程度の「余裕」があるという結果になると思われる。
従って1.8倍程度の「余裕」は、もはや余裕ではないと考えるべきなのではないだろうか。だからこそ福島第一のストレステストこそ一番に行うべきだったのだ。
福島第一原発で観測した揺れはSsの1.1倍ほどだった。それが多くの機器類を破損させ、おそらく冷却系配管の一部を破壊した。それが正確に評価できるテストでなければ意味は無い。
具体的にどこがどのように破壊されたかは依然として不明だが、1号機では隔離時復水器(IC・非常用復水器と誤って表記されることが多い)につながる配管、あるいはICそのもの、2、3号機はおそらくECCS系の配管や再循環系配管、これまでのバックチェックでも一番弱いとみられている原子炉隔離時冷却系配管が損傷しているかもしれない。
この原子炉隔離時冷却系・RCICというのは、電源喪失を起こした際に最後まで冷却水を炉内に送るためのタービン駆動ポンプがつながっている系統で、本来ならば電源喪失後も最後まで破壊されないように、最も強固に作るべきものだと思うのだが、実際には安全保護系の中では最も脆弱である。つまりSsに匹敵する地震に襲われると最初に破壊されるのが最後まで駆動を期待されているポンプだという、実に信じられないほど強度不足の装置なのだ。
こんな指摘をすれば、以前の東電は「そのような事態になればECCSが働く」「必要なポンプ駆動用電力は非常用ディーゼル発電機で供給する」と答えていた。
今回の事故の謎(たくさんあるがそのうちのひとつ)は、RCICがどうして止まったか(または止めたか)が分からないことだ。地震による損傷が原因の一つである可能性は高いと思われる。